
|
解説
「学社融合」
講師 文部省生涯学習局社会教育官 荒谷信子
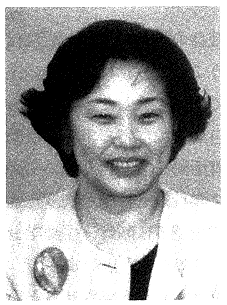
皆さん、おはようございます。
きょうは、与えられました1時間、「学社融合」について解説をさせて頂きます。「学社融合」は「学社連携」をさらに進めて、積極的に学校教育と社会教育が連携し、より豊かな教育を子供たちに提供しよう、ということで、この用語を使うことにいたしました。このように方向づけはしたものの、実践はこれからです。皆様方におかれましては、学社融合についてはこう考える、あるいはこんないい事例があるということをいろいろと私どもの方に情報提供していただくようお願いを申し上げます。
最近は融合という言葉をよく見聞きするようになりました。例えば、核融合であるとか、東西ドイツの融合、遺伝物質の融合説、あるいは情報処理におけるファイルとデータの結合など、いろいろと言われておりますが、辞典を引いてみますと、2つ以上の組織や成分が一緒になってよくまじり合い、全くもとの組織や、成分の跡をとどめていない状態になることをいう、とありました。
筑波大学の山本恒夫教授によりますと、学社融合というのは、連携では対処できない事態に直面したり、あるいは連携てばなし得ないものをつくり出す必要に迫られてきたときに生じる用語で、広い意味では学校と社会のさまざまな教育や学習活動が、狭い意味では学校教育と社会教育が、その一部を共有したり、両者共有の教育活動をつくり出すことであると定義をされておられます。
文部省では、学社融合について、これは学校教育と社会教育の融合を略した用語であって、学校教育と社会教育がお互いの役割分担を前提とした上で一歩踏み込んで、両者の要素を部分的に重ね合わせることにより、一体となって子供たちの教育に取り組んでいこうという考え方に立っております。したがいまして、学杜融合はこれまで、皆様方が随分努力をしてこられた学校連携の概念と決して対立するものではなく、むしろ学社連携の最も進んだ形態と言えます。
次に、学社融合と考えられる例ですが、地域の人たちや社会教育の専門家が学校の講師などとして授業を行う。学校教育の一環として社会教育施設等の社会教員の場を利用する。地域のいろいろな場で学校の教育が研修できる機会をつくる。地域でボランティア活動をしたことを学校の評価に位置づける週末などに学校の施設を活用して親子学習教室を開く。このようなことが考えられます。
それでは、今、なぜ学社融合なのか、ということでございます。子供たちの生活の実態を見てみますと、子供たちは非常にゆとりのない生活をしております。確かに物質的な豊かさや便利さの中で生活しておりますけれども、その一方で、夜眠れない、疲れやすい、朝、食欲がない、何となく大声を出したくなる、原因は不明だけれども、いらいらする。まるで大人たちが言っているようなことを子供たちが言っているんですね。ストレスがたまっているという状況がうかがえます。
健康・体力の問題を見てみますと、身長や体重など体格面では着実に向上していま九その反面で、肥満が増加していたり、視力が低下していたり、瞬発力、筋力、持久力、柔軟性は全般的に低下しています。その原因は、日常生活の中で運動の機会が減
前ページ 目次へ 次ページ
|

|